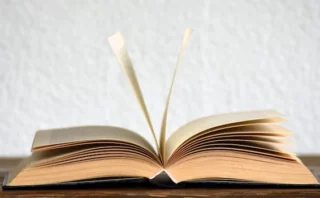以前にもこのブログで紹介しましたが、3か月に1度、事業会社で人材開発・組織開発を担っている皆さんと情報交換会を開催しています。(→ 以前に紹介したブログ記事へ)

今回のブログでは、この会へ初めて参加される皆さんから「どうしてこういった会をやろうと思ったのですか?」と聞かれることがありますので、その理由を書きます。
ついでに、直近に開催しました情報交換会の様子を共有します。
*************************
理由1.社外との交流機会を保持したいから
2023年9月に前職(パーソル総合研究所)から現在の会社(パナソニック インダストリー社)へ転職する際、それまでの経験で出会った皆さんとの交流を絶やしたくないという思いがありました。
社外からコンサルタントという立場でクライアント(事業会社)の人材開発・組織開発支援を行っていた際に、クライアント先で熱意のある皆さんと出会いました。そういった皆さんとのお付き合いの中で得られた知識や経験が、間違いなく現在の私を形作っています。
ですので、そんなご縁を途絶えさせないために何かできないかと思い、私も事業会社の側になりますので、皆さんと(同じ立場で)情報交換会をやりたいと思ったのが理由の1つ目です。

転職する際に業界が異なりましたので、競業避止義務を気にしなくて良かったこともポイントです。
理由2.セミナー・ウェビナーには限界があるから
人材開発・組織開発関連の講演(セミナー・ウェビナー)は様々なところで行われています。パーソル総合研究所に勤務していた時はそういったイベントを提供する側でした。
例えば、こんなことをやっていました。
*立教大学 中原先生との講演 → 関連サイトへ
*NTTドコモさんとの事例発表 → 関連サイトへ
事業会社へ転職して以降、様々な講演に参加してみて思うことが幾つかありました。
例えば、大学の先生や事業会社のトップマネジメント(CHRO・人事担当役員)、大手企業の人材開発・組織開発の部門長クラスのご講演を聞いたあと、
▲ 聞きたいことがあっても、イベントの環境的(大人数、オンライン視聴環境)に聞きづらい
▲ 聞きたいことをチャットで質問しても(質問が多いのか)取り上げてもらえない
▲ 講演内容にはない、現場レベルの工夫や苦労などもっとミクロなことを聞きたいが聞けない
▲ 聞きたいことをアンケートで聞いても回答がない/担当営業から的外れな回答しかもらえない
▲ 聞きたいことをアンケートに書き残すと、あとでベンダーからの営業が来るので、何となく面倒に感じる(ので書かない)
といった感想を持っています。ですので、講演の類いは「なんとなく良い話を聞けた感じがするけど、何が学べたかは分からない」といった結果になりがちです。

上手に学べていない責任は自分にあるとも思いますが・・・。
講演以外の、例えば、コンサル会社や研修ベンダーが主催する人数限定(20名程度)のイベントも、結局は講演者の方が中心の時間になりがちで、参加者どうしの交流はさほど促されません。
懇親会があったとしても、コンサル会社や研修ベンダーの方々が介在し、妙に気を遣う。結果として、参加者どうしはその場限りのご縁。その場限りでない関係性を作るのはなかなか難しいです。
これが、情報交換会をつくろうと思った理由の2つ目です。
*************************
そこで・・・
自分にとっても、参加される皆さんにとっても有益な場(楽しくて、ためになる場。そして、継続する場)ってどのような場なのかを考えたとき、以下のような要素が必要かなと思いました。
① 事業会社の人材開発・組織開発担当者だけで集まる ※コンサルや研修ベンダーは関与しない
② 集まっている場に一体感がある → 場の人数は20名くらいがMAXか
③ 毎回テーマを用意し、双方向でのやりとりの時間がたっぷりある ※長すぎてもいけない
④ ちょっとだけ、規律やルール、スケジュールのようなものがある ※ゆるすぎてもいけない
⑤ 定期開催する
⑥ 話題や場を少しだけピリッと締めてくださる方がいる(大学の先生、民間研究者)
⑦ 懇親会がある ※強制参加ではない

船中八策のようなものかな・・・
そして、こんなアイデアを、①以前からお付き合いのあった皆さん(A社のY.Mさん、ND社のM.Mさん&Y.Mさん、N社のK.Uさん)や、②比較的最近に出会って意気投合した皆さん(K社のN.Rさん、S社のT.Tさん)にお話しし、2024年8月に情報交換会がスタートしました。
これまでに5回開催し、一度でも参加された方の数は50名くらい(社数は25社くらい)を超えましたが、各回の参加上限者数は上記②の理由から20名としています。参加をお断りすることもあり、心苦しいときもありますが、そのように運営しています。
今のところ、ご参加の皆さんからはポジティブな感想をたくさんいただいております。

*************************
直近の情報交換会 実施報告
直近の会(第5回:7月25日開催)のテーマは「オンボーディング」でした。
せっかく獲得した人材にどう活躍してもらうか、人材の流動性が少しずつ高まっているとされている日本において、オンボーディングはますます重要なテーマになりそうかと思ってのテーマ設定です。
新卒入社者、中途入社者だけでなく、組織間異動者を対象に含めたオンボーディング施策には、各社が様々な工夫を凝らされており、同時に(似たような)悩みもお持ちの様子でした。
ご参加の皆さん、お疲れ様でした!
上記⑥に関連して、今回はゲストに 甲南大学 経営学部の尾形真実哉先生 をお呼びしました。(以下の写真で立っておられる方です)

尾形先生は、ずっと以前よりオンボーディングに関する研究をなさっておられ、この領域の第一人者です。ご著書も評判ですので、ご関心があれば是非お読みください!
尾形先生のご著書
・組織になじませる力 → Amazonへ
・中途採用人材を活かすマネジメント → Amazonへ
・若年就業者の組織適応 → Amazonへ
※「オンボーディング」という言葉が普及する前は「組織適応」とか「組織社会化」、「組織再社会化」という言葉が使われていました。
会の最後に尾形先生からコメントをいただきました。「オンボーディングにおいては、やはり職場のマネジャーが鍵を握ります。入社者・異動者への施策も大事ですが、結局はそこです」と。

やっぱりそうだよなぁ、と思って聞いていました。
尾形先生、ご参加いただき、ありがとうございました!またお越しください。
*************************
上記⑦の通り、情報交換会後には必ず懇親会を用意しています。ここまでをやってこその情報交換会かな、と思っています。(SPビールのTさん、毎度ありがとうございます!)
情報交換会での話の続きをしたり、プライベート(趣味や休日の過ごし方など)な話を交わしたりと、真面目さと楽しさの混ざりあった、とても愉快な場になっています。
以下の写真は今回の懇親会のときのものです。(妙なポーズは気にせずに)

ご参加の皆さん、楽しかったですね。参加できなかった皆さん、次の機会に!
※今回のサムネは、この懇親会で皆さんからもらった一皿です。皆さん、ありがとうございます!!
なお、懇親会への参加は任意です。情報交換会には参加できなかった(しなかった)けれども、懇親会だけでも参加したいという方がおられれば大歓迎としています。
毎回、数名の参加者が帰り際に「こういう場ってありそうでないんです。ホントにいい場ですね。また来たいです」とニコニコ笑顔でおっしゃられています。(多少のお世辞もあると思いますけど)

この笑顔と言葉が私のモチベーションになっています。
*************************
次回は「育成上手」をテーマに、という話が出ています。面白そうです。他にテーマアップがなければ、企画しようと思います。
個人的には、皆さんと話し合いたいテーマが他にも幾つかあります。情報交換会とは別に、ご参加の皆さんと個別にお会いし、学び合いの機会を持ちたいくらいです。
皆さんも、私でよければお気軽にお声掛けくださいー!